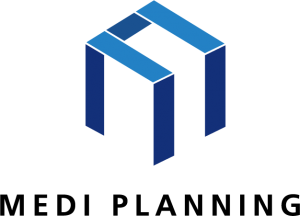
2025.05.02トレンド・ニュース
医師の長時間労働は以前から問題視されてきましたが、近年の高齢化による患者数の増加により、過労による離職も深刻化しています。医療体制は今なお逼迫しており、特に大学病院や総合病院などに勤務する医師の負担は大きいものがあります。オンコールによる呼び出しで実質的に自宅待機となるケースも多く、心身ともに休まらない状況が続いています。
一方で、開業医は診療時間や休日をある程度自ら調整できる立場にあり、働き方の自由度は高まります。ここでは、開業医の業務内容や休日事情、注意すべき点について紹介します。
開業医は診療だけでなく、経営・労務管理・書類作成など、多岐にわたる業務を担います。具体的にはスタッフのマネジメント、診療報酬請求関連の事務、医師会や保険医協会の活動、学会・講演・研修会への出席、画像読影や紹介状の作成などが含まれます。診療時間外にも多くの業務が発生するのが実情です。
クリニックを開業すれば、診療科や病院の体制にもよりますが、勤務医のようなオンコール対応は基本的に発生しません。しかし、前項で述べたように、診療時間外にも多くの業務に追われます。
神奈川県保険医協会の調査によると、開業医の実質的な週休数は以下のとおりです:
・週1日休み:29.3%
・週2日休み:27.7%
・週1.5日休み:14.3%
・週0日休み:1.9%
・週0.5日休み:3.6%
この結果からも、週休二日にはほど遠い実態が浮かび上がっています。
参考資料:神奈川県保険医協会|開業医の働き方調査
開業医は経営者としての業務を一手に引き受ける必要があり、業務量は非常に多岐にわたります。そのうえで医療知識のアップデートも欠かせず、過労や体調不良、精神的な負担により休業を余儀なくされるケースもあります。こうしたリスクに備え、多くの開業医が休業保障保険に加入しています。
全国保険医団体連合会に加盟する保険医協会・保険医会の会員向けに提供されている共済制度です。入院だけでなく自宅療養、短期間の再発による休業にも対応し、比較的低額な掛金で加入可能です。
・60歳未満であること
・加盟協会の会員であること(京都府保険医協会を除く)
・保険医であること
・主たる医療機関で週4日以上、16時間以上勤務していること
・現在健康であること
・傷病休業給付金:通算500日まで支給
・長期療養給付金:500日超の休業で最長230日まで
・その他:死亡・高度障害・脱退時の給付など全6種類の給付制度あり
・自宅療養でも、第三者の医師の診療を受けていれば給付対象
・休診せずに代診を立てた場合も給付対象となる
開業医は勤務医に比べて自由度が高い一方で、担う業務は多岐にわたり、過重労働に陥るリスクもあります。自分で働き方を調整できるとはいえ、無理のない体制づくりが重要です。適切な業務分担やスタッフとの連携を意識し、持続可能な診療体制を構築することが、クリニック全体の安定と成長につながります。院長自身の健康がクリニックの安心感にも直結するため、リスク管理とワークライフバランスの確保を心がけましょう。