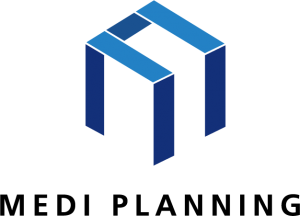
2025.10.22成功するクリニック経営
近年、電子カルテはクリニック経営に欠かせない存在となりました。しかし、導入後に「操作が複雑で現場が混乱した」「サポートが思ったより弱かった」と後悔する医師も少なくありません。電子カルテはただの便利なITツールではなく、診療の流れそのものを左右する医療インフラなのです。
ここでは、開業医や開業を予定する先生方が導入時に押さえておきたい比較ポイントを整理します。
電子カルテ選びで最も大切なのは、「自院の診療フローにどれだけ自然に馴染むか」です。機能の多さに目を奪われがちですが、入力が複雑だと診療スピードが落ち、患者とのやりとりに支障をきたす場合もあります。
導入前には、必ずデモを体験し、実際の外来業務を想定して操作感を確認しましょう。テンプレートのカスタマイズ性、ショートカット設定、音声入力、タブレット対応などもポイントです。訪問診療を行う場合は、院外アクセスやオフライン対応の有無も要チェックです。
電子カルテ導入の際には、どうしても初期費用に目が行きがちですが、長期的な観点からのトータルコストに着目する必要があります。月額利用料や保守費用、クラウド利用料、アップデート費用など、ランニングコストを合計すると想定以上に高額になることもあります。
また、システムトラブル時のサポート体制も重要です。診療中に不具合が発生した際、すぐに電話がつながるか、土日祝日の対応があるかを確認しましょう。
さらに、セキュリティやバックアップ体制も見逃せません。災害やサイバー攻撃など、万一の事態に備えたデータ保護体制を整えているベンダーを選ぶことが、安定した運用につながります。
電子カルテは単独で完結するものではなく、検査機器・レセコン・予約システム・オンライン資格確認などとの連携が重要です。導入前に、どこまで連携できるか、将来的な拡張にも対応可能かを確認しておきましょう。
特に、近年主流のクラウド型電子カルテは、導入のしやすさとアップデートの自動化が魅力ですが、通信障害リスクやカスタマイズ制限には注意が必要です。一方のオンプレミス型は安定性や自由度が高い反面、保守やセキュリティの管理負担が増えます。
今後、電子処方箋やPHR(Personal Health Record)など、医療DXの進展により連携の重要性はさらに高まります。法改正や制度変更への柔軟な対応力を持つベンダーかどうかも、長期運用のカギとなります。
電子カルテ導入は、単なるIT投資ではなく、診療スタイルの再設計です。導入後に後悔するケースの多くは、比較検討が十分でなかったことに起因します。
まず、自院の診療方針・人員体制・将来構想を整理したうえで、複数の候補を比較しましょう。最低でも三社はデモを試し、実際に操作してみることをおすすめします。現場スタッフの意見も取り入れ、操作性・サポート・コストなどを多角的に評価することが重要です。
実際に医業して電子カルテを使用している医師から、現場でも使用感やベンダーの対応について、生の情報を仕入れるのもいいでしょう。
電子カルテは、医療の質や患者満足度、スタッフの働きやすさを左右する中核的なシステムです。慎重な比較と十分な準備が、導入後の後悔を防ぎ、クリニックの成長を支える最善の投資となるでしょう。